全Aネット
NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会(全Aネット)

障害者の就労を支援する企業や福祉施設、NPO法人等から成る全国組織「就労継続支援A型事業所全国協議会(全Aネット)」は、2015年に設立され、障害者が雇用契約を締結して働く「A型」事業所の「在るべき姿」を全国的な情報交換と論議を通じて検討し、政策提言に繋げる場として活動しています。事業者の質的向上と、障害者の「労働の可能性」を拡大しエンパワメントを図るとの設立趣旨に賛同して、全国の多くの事業者が参加しています。
研進は、社会福祉法人進和学園の営業窓口会社であり、独自に「A型」も「B型」も営んでいませんが、設立以来、会員となり参加しています。
*「全Aネット」公式ホームページ ⇒ http://zen-a.net/
研進は、社会福祉法人進和学園の営業窓口会社であり、独自に「A型」も「B型」も営んでいませんが、設立以来、会員となり参加しています。
*「全Aネット」公式ホームページ ⇒ http://zen-a.net/
全Aネット「みなし雇用研究会」報告/障害者就労促進発注制度の実現に向けて

NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会(全Aネット)は、2020年6月26日付 Press Releaseにおいて、日本財団の助成を得て実施した「障害者みなし雇用研究会」(座長:諏訪康雄法政大学名誉教授)の報告を行いました。一般労働市場での就労が難しい障害者に多様な働き方を実現すべく、企業での直接雇用に加えて福祉事業所等への仕事の発注を促す「障害者就労促進発注制度」の創設を提言しています。
当初、研究会では、企業が福祉事業所等へ仕事を発注した場合に、当該企業の障害者法定雇用率に加算する、いわゆる「みなし雇用制度」の導入を意図していましたが、国の障害者就労対策の機軸である「直接雇用」への配慮から、現時点では、雇用率に上乗せするという制度ではなく、企業の発注を納付金の減額や調整金・報奨金の増額に止め、「みなし雇用」という表現も避けた制度を提言しています。
「みなし雇用制度」の導入を切望する立場からは、残念ながら期待していた内容には至りませんでしたが、「労働施策」と「福祉施策」に跨る複雑かつ難解な課題を正面から取り上げ、企業へのアンケート調査も行い、一般就労が困難な障害者の「働き方改革」にも繋がる方策を真剣に議論し具現化すべき方向性を示した意義は大きいと言えます。
当初、研究会では、企業が福祉事業所等へ仕事を発注した場合に、当該企業の障害者法定雇用率に加算する、いわゆる「みなし雇用制度」の導入を意図していましたが、国の障害者就労対策の機軸である「直接雇用」への配慮から、現時点では、雇用率に上乗せするという制度ではなく、企業の発注を納付金の減額や調整金・報奨金の増額に止め、「みなし雇用」という表現も避けた制度を提言しています。
「みなし雇用制度」の導入を切望する立場からは、残念ながら期待していた内容には至りませんでしたが、「労働施策」と「福祉施策」に跨る複雑かつ難解な課題を正面から取り上げ、企業へのアンケート調査も行い、一般就労が困難な障害者の「働き方改革」にも繋がる方策を真剣に議論し具現化すべき方向性を示した意義は大きいと言えます。
「はたらくNIPPON!計画」A型シンポジウム in 横浜/A型事業のあり方を考える
NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会(全Aネット)主催の「はたらくNIPPON!計画」A型シンポジウム in 横浜 が、2018年2月24日、横浜市開講記念館において開催されました。全国より200名以上が参加し、A型(雇用型)事業を中心とする福祉的就労の在り方を考える上で、貴重かつ有益な機会となりました。
厚生労働省からの行政説明、本取り組みを助成する日本財団からの報告を受けた後、全Aネット研究会報告書(骨子案)について、岩田克彦委員長(労働政策研究・研修機構客員研究員)より要点解説・提言が為されました。その内容を踏まえたシンポジウムでは、岩田委員長が座長を務め、村木太郎(全国シルバー人材センター事業協会専務理事)、丸物正直(全国重度障害者雇用事業所協会専務理事)、米澤旦(明治学院大学准教授)、久保寺一男(全Aネット理事長)各委員によるディスカッションが組まれました。研究会報告書(骨子案)は、昨今、顕在化している悪しきA型事業所の実態を踏まえ、当該事業の経営に関する諸問題、精神障害者に対する就労支援、一般就労への移行施策、障害者以外の就労困難者の受入れ、職員の量・質の確保等、広範な課題を掲げています。良質な仕事の確保のため、「民需」における発注促進策、特に、企業における障害者の直接雇用に加えて、発注/業務委託(請負)形態の場合も発注企業の法定雇用率の一部に加算する「みなし雇用制度」(注)の導入についても提言されています。
A型事業が、「雇用」と「福祉」にまたがる中間的就労の特性と可能性を活かして、健全な形で発展し「在るべき姿」を追求するためにも、全Aネットの取り組みは注目され大きな期待が寄せられています。
厚生労働省からの行政説明、本取り組みを助成する日本財団からの報告を受けた後、全Aネット研究会報告書(骨子案)について、岩田克彦委員長(労働政策研究・研修機構客員研究員)より要点解説・提言が為されました。その内容を踏まえたシンポジウムでは、岩田委員長が座長を務め、村木太郎(全国シルバー人材センター事業協会専務理事)、丸物正直(全国重度障害者雇用事業所協会専務理事)、米澤旦(明治学院大学准教授)、久保寺一男(全Aネット理事長)各委員によるディスカッションが組まれました。研究会報告書(骨子案)は、昨今、顕在化している悪しきA型事業所の実態を踏まえ、当該事業の経営に関する諸問題、精神障害者に対する就労支援、一般就労への移行施策、障害者以外の就労困難者の受入れ、職員の量・質の確保等、広範な課題を掲げています。良質な仕事の確保のため、「民需」における発注促進策、特に、企業における障害者の直接雇用に加えて、発注/業務委託(請負)形態の場合も発注企業の法定雇用率の一部に加算する「みなし雇用制度」(注)の導入についても提言されています。
A型事業が、「雇用」と「福祉」にまたがる中間的就労の特性と可能性を活かして、健全な形で発展し「在るべき姿」を追求するためにも、全Aネットの取り組みは注目され大きな期待が寄せられています。
全Aネット 全国実態調査報告会/A型事業所の現状と課題

NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会(全Aネット)は、ヤマト福祉財団からの助成を受け、全国の就労継続支援A型事業所の実態調査を行い、今般、報告書を取り纏めました。
2017年9月12日、報告書の説明会が参議院議員会館において開催され、NHK、毎日新聞社はじめマスコミの取材も受ける貴重な機会となりました。
冒頭挨拶に立った全Aネットの久保寺一男理事長は、「悪しきA型事業者(福祉予算を目当てとする不適格な事業者)を許さない。一般就労が難しい障害者や社会的弱者に労働者として権利を保証する健全なA型事業者の在るべき姿を目指す」という全Aネットの設立趣旨に沿った取り組みであることを説明。調査・研究委員会の岩田克彦委員長(労働政策研究・研修機構 客員研究員)から、報告書の概要が披露され、質疑応答が行われました。
報告書HPIMG_0040.jpgA型事業所の現状と課題が、具体的なデータに基づき明らかにされ、今後、取り組むべき事項が示されました。特に、多くのA型事業所が、就労支援事業(作業会計)単独では赤字であり、公的資金である給付費や補助金収入(福祉会計)への依存が大きい実情から、「良質な仕事の確保」が重要な優先課題であることを指摘しています。「良質な仕事の確保」のためには、「企業に対する発注奨励の実現」を掲げ、企業がA型事業所等に仕事を発注した場合に、その分を発注企業の障害者法定雇用率に加算する「みなし雇用制度」の導入を検討すべきことを政府への要望事項として明記しています。
「みなし雇用制度」については、私達もその必要性を従前から提言して来ましたが、全Aネットの取り組みが同制度の導入を促し、福祉的就労の底上げに繋がることを期待したいと思います。
2017年9月12日、報告書の説明会が参議院議員会館において開催され、NHK、毎日新聞社はじめマスコミの取材も受ける貴重な機会となりました。
冒頭挨拶に立った全Aネットの久保寺一男理事長は、「悪しきA型事業者(福祉予算を目当てとする不適格な事業者)を許さない。一般就労が難しい障害者や社会的弱者に労働者として権利を保証する健全なA型事業者の在るべき姿を目指す」という全Aネットの設立趣旨に沿った取り組みであることを説明。調査・研究委員会の岩田克彦委員長(労働政策研究・研修機構 客員研究員)から、報告書の概要が披露され、質疑応答が行われました。
報告書HPIMG_0040.jpgA型事業所の現状と課題が、具体的なデータに基づき明らかにされ、今後、取り組むべき事項が示されました。特に、多くのA型事業所が、就労支援事業(作業会計)単独では赤字であり、公的資金である給付費や補助金収入(福祉会計)への依存が大きい実情から、「良質な仕事の確保」が重要な優先課題であることを指摘しています。「良質な仕事の確保」のためには、「企業に対する発注奨励の実現」を掲げ、企業がA型事業所等に仕事を発注した場合に、その分を発注企業の障害者法定雇用率に加算する「みなし雇用制度」の導入を検討すべきことを政府への要望事項として明記しています。
「みなし雇用制度」については、私達もその必要性を従前から提言して来ましたが、全Aネットの取り組みが同制度の導入を促し、福祉的就労の底上げに繋がることを期待したいと思います。
NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会(全Aネット)は、ヤマト福祉財団からの助成を受け、全国の就労継続支援A型事業所の実態調査を行い、今般、報告書を取り纏めました。
2017年9月12日、報告書の説明会が参議院議員会館において開催され、NHK、毎日新聞社はじめマスコミの取材も受ける貴重な機会となりました。
冒頭挨拶に立った全Aネットの久保寺一男理事長は、「悪しきA型事業者(福祉予算を目当てとする不適格な事業者)を許さない。一般就労が難しい障害者や社会的弱者に労働者として権利を保証する健全なA型事業者の在るべき姿を目指す」という全Aネットの設立趣旨に沿った取り組みであることを説明。調査・研究委員会の岩田克彦委員長(労働政策研究・研修機構 客員研究員)から、報告書の概要が披露され、質疑応答が行われました。
報告書HPIMG_0040.jpgA型事業所の現状と課題が、具体的なデータに基づき明らかにされ、今後、取り組むべき事項が示されました。特に、多くのA型事業所が、就労支援事業(作業会計)単独では赤字であり、公的資金である給付費や補助金収入(福祉会計)への依存が大きい実情から、「良質な仕事の確保」が重要な優先課題であることを指摘しています。「良質な仕事の確保」のためには、「企業に対する発注奨励の実現」を掲げ、企業がA型事業所等に仕事を発注した場合に、その分を発注企業の障害者法定雇用率に加算する「みなし雇用制度」の導入を検討すべきことを政府への要望事項として明記しています。
「みなし雇用制度」については、私達もその必要性を従前から提言して来ましたが、全Aネットの取り組みが同制度の導入を促し、福祉的就労の底上げに繋がることを期待したいと思います。
2017年9月12日、報告書の説明会が参議院議員会館において開催され、NHK、毎日新聞社はじめマスコミの取材も受ける貴重な機会となりました。
冒頭挨拶に立った全Aネットの久保寺一男理事長は、「悪しきA型事業者(福祉予算を目当てとする不適格な事業者)を許さない。一般就労が難しい障害者や社会的弱者に労働者として権利を保証する健全なA型事業者の在るべき姿を目指す」という全Aネットの設立趣旨に沿った取り組みであることを説明。調査・研究委員会の岩田克彦委員長(労働政策研究・研修機構 客員研究員)から、報告書の概要が披露され、質疑応答が行われました。
報告書HPIMG_0040.jpgA型事業所の現状と課題が、具体的なデータに基づき明らかにされ、今後、取り組むべき事項が示されました。特に、多くのA型事業所が、就労支援事業(作業会計)単独では赤字であり、公的資金である給付費や補助金収入(福祉会計)への依存が大きい実情から、「良質な仕事の確保」が重要な優先課題であることを指摘しています。「良質な仕事の確保」のためには、「企業に対する発注奨励の実現」を掲げ、企業がA型事業所等に仕事を発注した場合に、その分を発注企業の障害者法定雇用率に加算する「みなし雇用制度」の導入を検討すべきことを政府への要望事項として明記しています。
「みなし雇用制度」については、私達もその必要性を従前から提言して来ましたが、全Aネットの取り組みが同制度の導入を促し、福祉的就労の底上げに繋がることを期待したいと思います。
全Aネット研修会「中間的就労の場への仕事の発注促進策について」

NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会(全Aネット)及び(公)全国重度障害者雇用事業所協会が主催する研修会が、2017年2月28日、参議院議員会館において開催されました。「働きづらい人に良質な仕事を!」と題し、テーマとして「中間的就労の場への仕事の発注促進策について」を取り上げ約50名が参加しました。
村木太郎様(全国シルバー人材センター事業協会専務理事)を座長として、中島隆信先生(慶応大学教授)、内藤晃様(光明会・明朗塾常務理事)と共に、研進(進和学園の営業窓口会社)の出縄貴史が発題者を務めさせて頂きました。
全Aネット研修会hpIMG_2358.jpg研進からは、中核事業としてのホンダ車部品組立加工や地元スーパーとの連携に基づく施設外就労等の実績を踏まえ、障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度/特例調整金等」の可能性を展望し、「民需」における発注促進策についての問題意識及び提言を述べさせて頂きました。特に、企業における障害者の直接雇用に加えて、発注/業務委託(請負)形態の場合も発注企業の法定雇用率の一部に加算する「みなし雇用制度」の導入の必要性を指摘させて頂きました。
このような有意義な研修会の場で、発表・議論の機会を得ましたことは、誠に光栄なことと感謝申し上げます。障害者の一般就労のみならず、福祉施設で働く障害者の自立・就労支援についても実効性ある制度・施策の拡充が切望されています。
【弊社発表内容】
村木太郎様(全国シルバー人材センター事業協会専務理事)を座長として、中島隆信先生(慶応大学教授)、内藤晃様(光明会・明朗塾常務理事)と共に、研進(進和学園の営業窓口会社)の出縄貴史が発題者を務めさせて頂きました。
全Aネット研修会hpIMG_2358.jpg研進からは、中核事業としてのホンダ車部品組立加工や地元スーパーとの連携に基づく施設外就労等の実績を踏まえ、障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度/特例調整金等」の可能性を展望し、「民需」における発注促進策についての問題意識及び提言を述べさせて頂きました。特に、企業における障害者の直接雇用に加えて、発注/業務委託(請負)形態の場合も発注企業の法定雇用率の一部に加算する「みなし雇用制度」の導入の必要性を指摘させて頂きました。
このような有意義な研修会の場で、発表・議論の機会を得ましたことは、誠に光栄なことと感謝申し上げます。障害者の一般就労のみならず、福祉施設で働く障害者の自立・就労支援についても実効性ある制度・施策の拡充が切望されています。
【弊社発表内容】
「JL NEWS」(公益社団法人日本発達障害連盟)に記事掲載
公益社団法人 日本発達障害連盟 の機関誌「JL NEWS」2016年11月号No.108に、「全Aネットの取り組みと今後の課題」と題するレポート記事が掲載されました。NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会(全Aネット)の久保寺一男理事長(進和学園統括施設長)が、2015年2月末に設立された全Aネットの目的に照らし、約1年半の取り組みの進捗状況をレビューし今後の課題について簡略に報告しています。
「福祉」と「雇用」の中間的な就労分野において、A型(雇用型)事業が一定の役割を果たし、障害のある方々にとって貴重な就労機会をもたらすことが期待されています。A型事業所に健全な運営を促すと共に、法制度や各種施策の拡充に向けた提言を行う等、全Aネットの今後の取り組みに注目したいと思います。
「福祉」と「雇用」の中間的な就労分野において、A型(雇用型)事業が一定の役割を果たし、障害のある方々にとって貴重な就労機会をもたらすことが期待されています。A型事業所に健全な運営を促すと共に、法制度や各種施策の拡充に向けた提言を行う等、全Aネットの今後の取り組みに注目したいと思います。
日本経済新聞 中島隆信教授「障害者雇用の拡大へ/施設への業務委託活用を」
私共も、40年以上に亘る本田技研工業(株)様からの部品組立業務を受注して来た経験から、発注企業であるホンダ様に、より正当な社会的評価が付与されるべきとの問題意識を抱き続けて来ました。障害者の直接雇用に加えて発注形態の場合も企業の法定雇用率に加算計上する「みなし雇用」制度の導入は、我が国の福祉的就労の拡充に大きく貢献するものと考えます。「労働」と「福祉」を架橋するハイブリッド型の制度は、貧困状態に低迷する福祉施設に健全な競争原理を育み、障害者にディーセントワーク(Decent Work:人間らしい働き甲斐のある仕事)をもたらす上で大きな効果を有するものと確信します。
全Aネット主催 特別研修会 「A型事業所の質の評価を考える」
2016年2月17日、全Aネット(NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会)主催の掲題特別研修会が、BIZ新宿(新宿区立産業会館)において開催され、全Aネットの会員を中心に全国21都道府県より約100名が集いました。
厚生労働省(障害福祉課)の香月就労支援専門官より、A型(雇用型)事業関係の障害福祉施策の説明を受けると共に、松井亮輔法政大学名誉教授による「ディーセントワークを目指す就労継続支援A型事業等のあり方を考える」と題する講演が組まれました。
行政説明及び松井亮輔先生の講演に係わる質疑応答と合わせ全体討議の時間が用意され、A型事業の役割、課題・問題点、今後の方向性等について活発な意見交換が為されました。研進も参加し、①「質」を担保するための「仕事の確保」/企業への発注奨励策及び「みなし雇用」制度導入(注) ②福祉的就労における労働者性の認容 ③職業能力に応じた処遇/最低賃金減額特例の公平かつ合理的な適用等について意見を述べさせて頂きました。
厚生労働省(障害福祉課)の香月就労支援専門官より、A型(雇用型)事業関係の障害福祉施策の説明を受けると共に、松井亮輔法政大学名誉教授による「ディーセントワークを目指す就労継続支援A型事業等のあり方を考える」と題する講演が組まれました。
行政説明及び松井亮輔先生の講演に係わる質疑応答と合わせ全体討議の時間が用意され、A型事業の役割、課題・問題点、今後の方向性等について活発な意見交換が為されました。研進も参加し、①「質」を担保するための「仕事の確保」/企業への発注奨励策及び「みなし雇用」制度導入(注) ②福祉的就労における労働者性の認容 ③職業能力に応じた処遇/最低賃金減額特例の公平かつ合理的な適用等について意見を述べさせて頂きました。

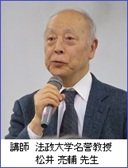
全Aネットでは、目下、A型事業者のプレ実態調査を進めていますが、今後、同事業の在るべき姿を提示し我が国の「福祉的就労」の拡充に資する政策提言に繋げて行くことが期待されます。A型事業が、「福祉」と「労働」施策双方に係わる中間的就労形態であるだけに、その果たす役割は大きいと考えます。






